心がラクになる10の法則

こんにちは。小学校で子どもたちの心に寄り添うカウンセラー、「こころ先生」です。
日々、子どもたちと接する中で、よくこんな声を耳にします。
「友だちに嫌われたかもしれない…」
「自分に自信がないんです…」
「失敗ばかりで、やる気が出ない…」
子どもたちは、大人が思っている以上にたくさんのことを感じ、考え、悩んでいます。
でも、その悩みを言葉にできなかったり、「こんなことで悩んでるなんてヘンかな?」と思ってしまったりすることも。
今日は、そんな子どもたちの悩みを少しでも軽くするために、
誰でも実践できる「10の法則」をご紹介します。
保護者の方や先生方も、日々のかかわりのヒントとしてご活用ください。
①「話す=放す」の法則

悩みは、心の中にため込むほど大きく見えるものです。
でも、誰かに話すことで、気持ちが整理され、心が軽くなります。
たとえば、
「先生に話したらちょっとスッキリした」
「友だちが“わかるよ”って言ってくれて安心した」
そんな経験、ありませんか?
話すことは、悩みを“放す”こと。
話せる相手がいることは、何よりの安心になります。
どうしてラクになるの?
人はつらいことを誰かに「話す」だけで、気持ちが軽くなります。
これは、話すことで脳の「扁桃体(へんとうたい)」という不安やストレスを感じる部分の働きがやわらぐからです。
また、信頼できる相手と話すと「オキシトシン」という安心ホルモンが分泌され、心が落ち着くとも言われています。
話すことは、悩みを「放す」こと。
安心できる相手に思いを伝えることが、心の健康を保つ第一歩です。
②「できたことをさがす」法則
子どもは、できなかったことや失敗に目を向けがちです。
でも、本当に大切なのは”できたこと”に気づく力。
- 宿題を最後までやった
- 苦手な子に「おはよう」が言えた
- 前より少し早く走れるようになった
そんな“小さなできた”を見つける習慣が、
「ぼく、やればできる!」という自信のタネになります。
どうしてラクになるの?
小さな「できた」に気づくと、脳から「ドーパミン」という“うれしい”ホルモンが出て、やる気がわいてきます。
このドーパミンは「達成感」や「よろこび」を感じたときに分泌されるため、小さな成功体験を積みかさねることで「またやってみよう」という前向きな気持ちが育ちます。
「失敗したこと」ではなく「できたこと」に注目する習慣が、自信を育てる力になります。
③「気持ちに名前をつける」法則
「なんかモヤモヤする」「イライラする」——
こうした漠然とした気持ちは、正体がわからないからこそ不安になります。
だからこそ、まずはその気持ちに“名前”をつけてみることが大切。
- 「かなしかったんだな」
- 「くやしかったんだね」
- 「不安になってたんだな」
そうやって感情を言葉にすることで、自分の心と向き合いやすくなります。
どうしてラクになるの?
イライラ、モヤモヤ、不安…そうした感情に「名前をつける」だけで、心は少し落ち着きます。
これは、感情を言葉にすることで、脳の中で気持ちを処理する「前頭前野(ぜんとうぜんや)」が活性化し、感情をコントロールしやすくなるからです。
名前がつくと「これは怒りだ」「これはさびしさだ」と整理できるようになり、気持ちに振り回されずにすむようになります。
④「比べるのは“他人”じゃなく“昨日の自分”」法則
つい友だちと自分を比べて落ち込んでしまう……それは誰にでもあることです。
でも、本当に大切なのは、自分自身の成長を見ること。
- 昨日より少しうまく書けた
- 先週より声が出せた
- 前よりちょっとだけ勇気を出せた
“自分比べ”は、子どもの自己肯定感をぐんと育ててくれます。
どうしてラクになるの?
他人と自分を比べると、脳は「自分は足りない」と感じてストレスをためやすくなります。
でも、昨日の自分と比べて「できるようになったこと」を見つけると、脳は「成長した!」と感じて自己肯定感が高まります。
これは、脳が変化や進歩をポジティブにとらえる性質があるためです。
比べるなら他人ではなく、少し前の自分。
これが心の健康にもとてもよい方法です
⑤「まちがい=学びのタネ」法則
「まちがえたらダメ」「失敗したら恥ずかしい」——
そんな気持ちが、チャレンジをさまたげてしまうこともあります。
でも、失敗やまちがいこそ、学びのタネです。
まちがいをきっかけに「じゃあ次はどうしよう?」と考えられることが、成長の一歩。
子どもがまちがえたときには、「ナイスチャレンジ!」と伝えてあげてください。
どうしてラクになるの?
まちがえたとき、脳は「どうしてまちがえたのかな?」と考える働きをします。
これは「誤り関連陰性電位(ERN)」と呼ばれる脳の反応で、学びにとって重要なサインです。
まちがいを「失敗」と見るのではなく「成長のきっかけ」ととらえると、脳は次に正しくやろうと活発に働きます。
だからこそ、まちがいを恐れず、「チャレンジしたこと」を認めることが大切です。
⑥「時間がたてば、ちがって見える」法則
そのときはすごくつらかったことも、時間がたつと「あれ、たいしたことなかったかも」と思えることがあります。
子どもは今この瞬間の気持ちに飲み込まれやすいからこそ、
「時間がたてば変わることもある」と伝えてあげましょう。
「明日になったらちょっと変わってるかもしれないね」
そんな声かけが、子どもの心に希望を灯します。
どうしてラクになるの?
悩みや不安な気持ちは、時間がたつと少しずつやわらいでいきます。
これは脳の中で、ストレス反応を調整する仕組み(副腎皮質ホルモンや自律神経など)がはたらくからです。
また、時間がたつことで、記憶の意味づけや感情の強さも変わり、「あのときは大変だったけど、今は大丈夫」と感じられるようになります。
感情はずっと同じではない、というのは脳科学でも明らかになっています。
⑦「“ひとりじゃない”を思い出す」法則
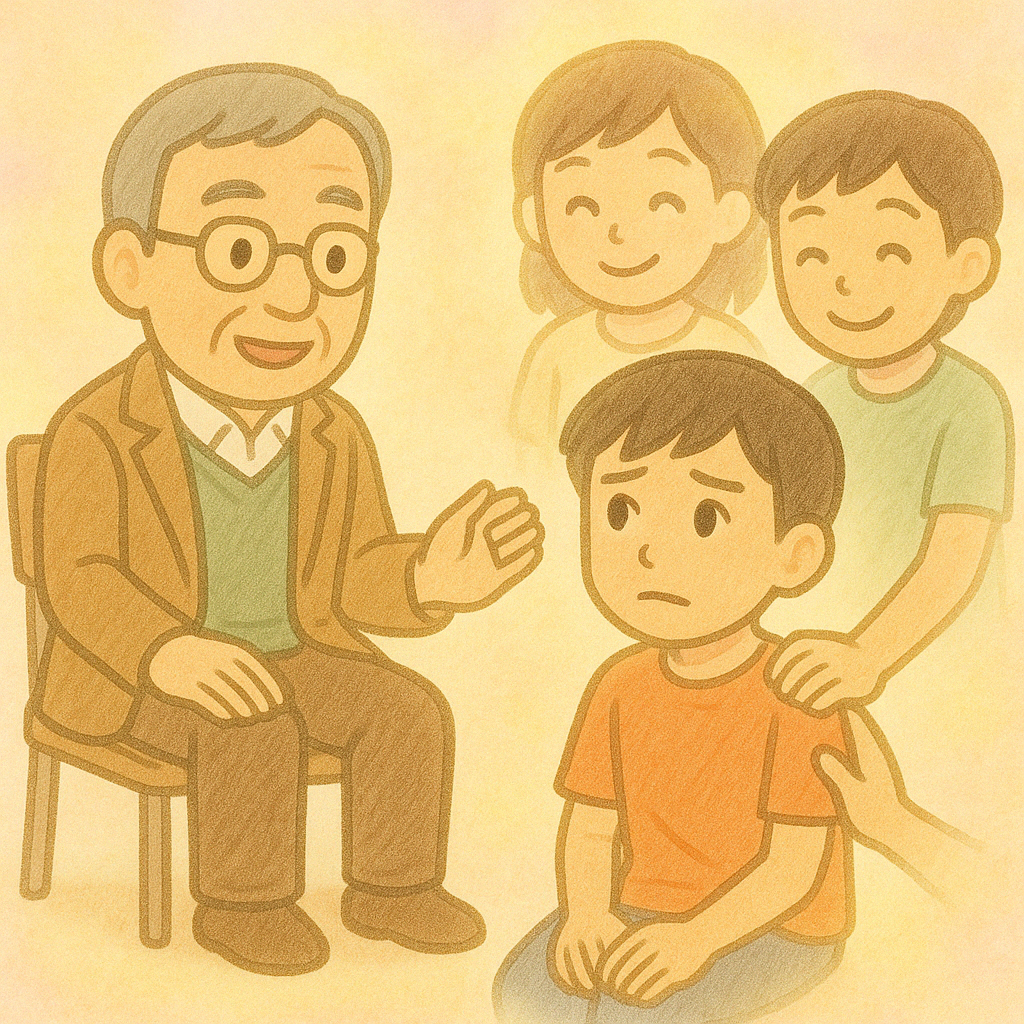
悩みを抱えるとき、人は「自分だけがつらい」と感じてしまいがちです。
でも、実はまわりには、見守ってくれている人がたくさんいます。
- 家族
- 先生
- カウンセラー
- 友だち
「何かあったら頼っていいんだよ」という安心感は、子どもにとって心の土台になります。
どうしてラクになるの?
誰かとつながっていると感じると、脳は「安心していいよ」という信号を出します。
これは「オキシトシン」というホルモンのはたらきで、人とのつながりやふれあいがあるときに分泌されます。
オキシトシンは「絆ホルモン」とも呼ばれ、心をあたたかく保ち、不安を減らす効果があるといわれています。
「ひとりじゃない」と思えるだけで、心の中にゆとりが生まれるのです。
⑧「“心”にも休けいが必要」の法則
頭や体が疲れるように、心も疲れます。
悩みごとをずっと考えていると、心がクタクタになってしまう。
そんなときは、いったん“考えない時間”をつくることも大切です。
- 好きな音楽を聞く
- 体を動かす
- 風にあたって深呼吸する
心にスペースができると、自然と前向きな考えがわいてくることもあります。
どうしてラクになるの?
勉強や人づきあいでつかれたとき、心にも“休けい”が必要です。
脳はずっと考えごとをしていると、ストレスホルモン(コルチゾール)がたまり、集中力ややる気がさがります。
でも、外で体を動かしたり、音楽を聞いたりしてリラックスすると、自律神経が整い、心が元気を取りもどします。
休けいは、さぼりではなく「回復のスイッチ」。
心のメンテナンスなのです。
⑨「助けを求めるのは“勇気”」の法則
「誰かに頼るのはカッコ悪い」「弱いと思われたくない」——
そんな思いでひとりでがんばりすぎる子もいます。
でも、本当に強い人は、助けが必要なときに「助けて」と言える人です。
「言ってくれてありがとう」
「相談してくれてうれしいよ」
そう伝えることで、子どもは安心してSOSを出せるようになります。
どうしてラクになるの?
誰かに「たすけて」と言うとき、人はとても大きな勇気を出しています。
実際に、助けを求めたときには脳の安心中枢がはたらき、「オキシトシン」や「セロトニン」などの安心ホルモンが出ることがわかっています。
また、助けを求めたあとで「わかってくれた」「受けとめてもらえた」と感じると、心の回復力(レジリエンス)がぐんと高まります。
SOSを出せる人は、じつは強い人なのです。
⑩「“自分らしさ”がいちばんの強み」法則
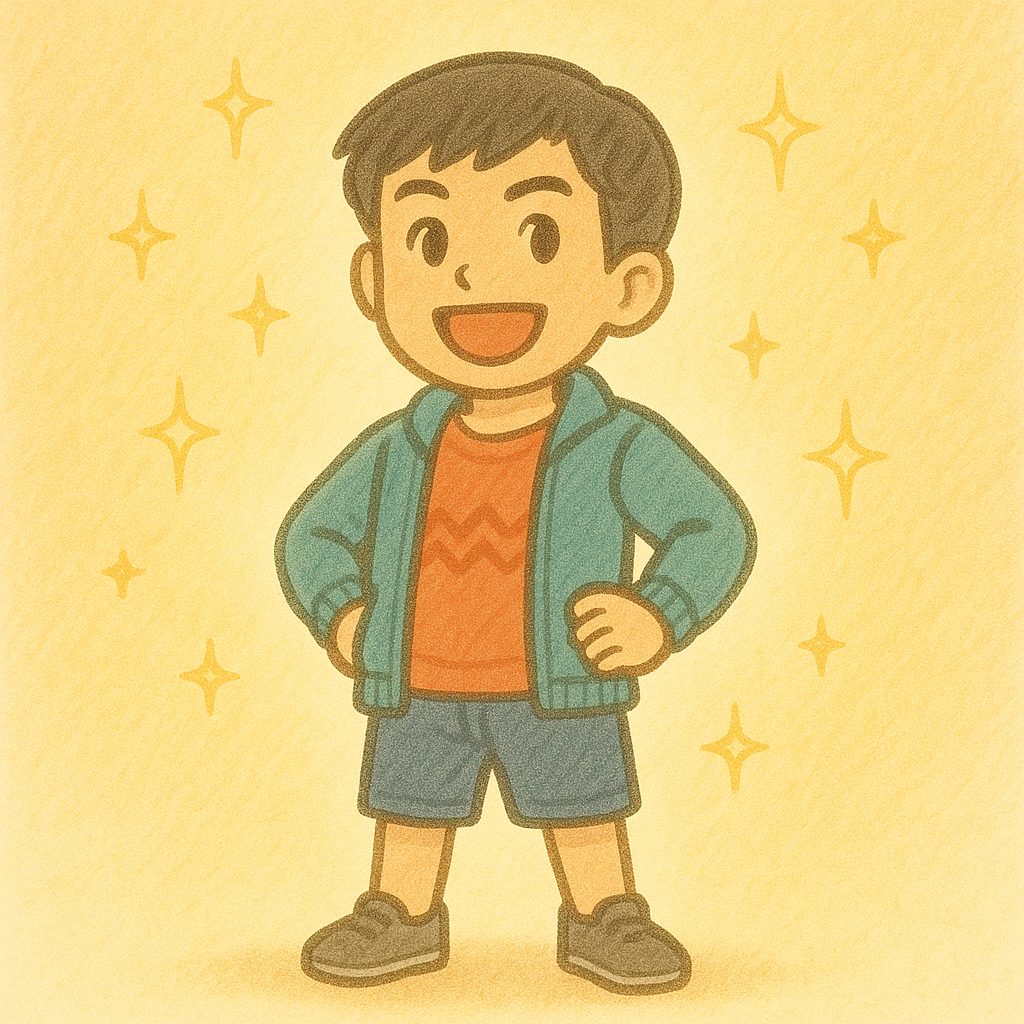
誰にでも得意・不得意はあります。
でも、まわりとちがうことは、“短所”ではなく“個性”です。
- おしゃべりが苦手→聞き上手
- じっとしてるのが苦手→行動力がある
- 細かい作業が得意→丁寧で観察力がある
その子の“らしさ”を見つけて伝えてあげることが、長く続く自信につながります。
どうしてラクになるの?
脳の使い方や得意なことは、人それぞれちがいます。
これは「多様な脳の特性(ニューロダイバーシティ)」といって、最近とくに注目されている考え方です。
計算が得意な子もいれば、おしゃべりが上手な子、じっと考えるのが好きな子もいます。
自分らしい特性を知り、認めることで、自信や安心感が生まれます。
「みんなちがって、みんなすごい」が、科学でもちゃんと証明されているのです。
おわりに
子どもたちが日々抱える悩みは、小さなことのように見えて、実はとても深くて大きいものです。
でも、ちょっとした考え方や声かけ、関わり方の中に、悩みを軽くするヒントはたくさんあります。
今回紹介した10の法則は、特別な道具も時間もいりません。
ただ、子どもの心にそっと寄り添い、「だいじょうぶ」と伝えるだけでいいのです。
子どもたちが「心の中に安心の場所」をもてるように。
その第一歩として、このブログが少しでもお役に立てたらうれしいです。

コメント